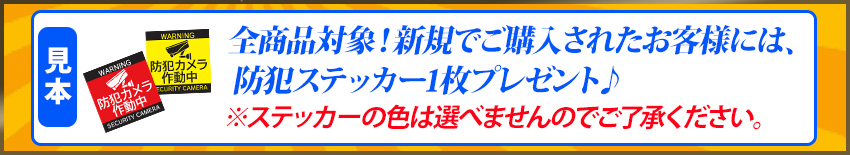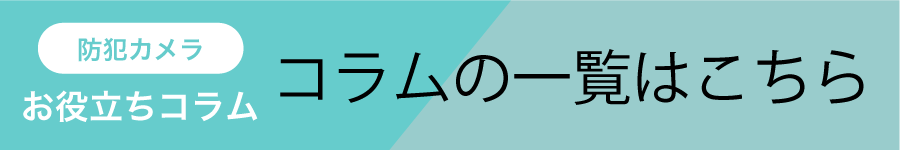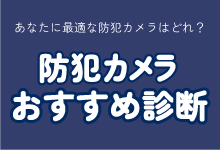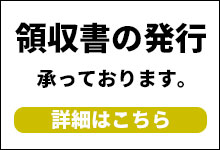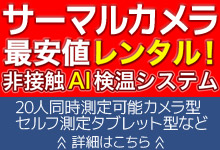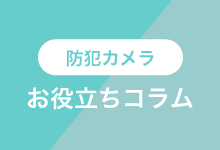防犯カメラに関するお役立ちコラムはこちら
防犯カメラの撮影範囲はどのくらい?確認方法や設置のポイントを解説

防犯カメラを購入する際に、どのくらいの範囲まで撮影ができるのか確認する方は意外と少ないものです。しかし、せっかく防犯カメラを設置しても、撮影したい場所が撮影できない事態に陥ってしまうこともあります。
そこで今回のコラムでは、防犯カメラの撮影範囲について解説していきます。撮影範囲を確認する方法や設置する際のポイントも紹介していきます。
撮影範囲を確認する際のポイント
防犯カメラの撮影範囲を確認するには、画角と撮影対象物までの距離を把握することが必要になります。そこで画角と撮影対象物までの距離について確認していきましょう。
防犯カメラの画角を把握する
画角とは撮影可能な範囲のことで、防犯カメラだけではなく、カメラ全般で使用される言葉です。水平方向(横)と垂直方向(縦)の画角があり、水平方向は「水平画角」、垂直方向は「垂直画角」と呼ばれるのが一般的です。表記は「◯◯度」と角度で表され、数字が大きいほど広い範囲が撮影できることを表しています。
一般的にレンズには「標準」「広角」「望遠」の3つの種類があり、それぞれ画角や焦点距離が異なります。
標準レンズ
画角は47度前後で、焦点距離は50㎜前後のレンズです。防犯カメラに標準で採用されているレンズと考えていいでしょう。焦点距離とは、撮影対象物にピントを合わせた時にレンズに入る光を電子情報に変換するイメージセンサーと、レンズの中心点までの距離を言います。防犯カメラの取り扱い説明書などには「f」を用いて焦点距離を表しています。「f=6」と記載されているカメラは、焦点距離、つまりイメージセンサーとレンズとの距離が6㎜ということを表しています。
広角レンズ
標準レンズよりも広い範囲を撮影できるレンズです。画角は63度前後で、焦点距離は35㎜以下となっています。画角が75度前後で、焦点距離が24㎜以下になると、より広範囲を撮影できる超広角レンズと言われることもあります。1台の防犯カメラで広い範囲を撮影できるのが特徴で、敷地の広い駐車場や、駅や商業施設などの広い空間内を撮影したい時などにふさわしいレンズです。ただし、細かな部分を明確に映すには向いていないとされます。
望遠レンズ
標準レンズよりも画角が狭く、遠くまでを撮影できるのが望遠レンズです。画角は24度前後で、焦点距離は100㎜以上になっています。レンズの焦点も遠くで合わせることができるので、遠い場所をピンポイントで撮影する際にも向いています。
このほか防犯カメラでは、特殊なレンズを採用しているケースもあります。代表的なのがバリフォーカルレンズ、PTZカメラ、360度カメラです。詳しく見てみましょう。
バリフォーカルレンズ
バリフォーカルレンズは、必要に応じて画角を調節できるレンズです。広角レンズと望遠レンズを組み合わせたような特徴を持っています。「全体を映すには画角を広げる」「詳細を確認したい場合は画角を狭める」といった使い方ができます。購入後に、防犯カメラの利用目的が変わるといったケースもありますが、その場合も柔軟に対応することが可能です。
PTZカメラ(レンズ)
PTZカメラ(レンズ)とは、レンズが上下左右、さらにズームアップ・ズームダウンするカメラのことです。レンズが上下に動くことをチルトといい、左右に動くことはパンと言います。撮影できる範囲はレンズの首振りに応じて広くなります。
360度カメラ
360度カメラは半球体のドーム型をしているカメラで、全方位を撮影することができます。死角が少ないため、商業施設やスーパーマーケット、イベント会場といった広い場所を監視する際などに用いられています。ただし、デメリットもあります。360度カメラでは、映像が大きく歪んでしまうという特徴があるからです。撮影後に映像を修正することもできますが、詳細を確認したい場合には手間がかかることもあります。
撮影したい対象物までの距離を把握する
画角を把握するとともに、防犯カメラの撮影可能範囲を確認するために必要なのが、撮影する予定の対象物までの距離です。例えば、屋外に停めている車を撮影したいのであれば、カメラの設置予定場所から車までの距離を測ることで把握することができます。より正確に撮影範囲を確認したい場合は、レーダー距離計などを使用して正確な数値を割り出すことがおすすめです。
一般的に、撮影対象物までの距離が近いほど対象物は大きく映る一方、防犯カメラで撮影できる範囲は狭くなります。その反対に、撮影対象物までの距離が遠いほど対象物は小さく映り、撮影可能範囲は広くなります。
撮影範囲を確認する方法
画角と撮影対象物までの距離を把握したところで、防犯カメラの撮影範囲を確認する方法を紹介しましょう。三角関数の公式を用いて計算することになります。
撮影可能範囲=tan(画角÷2)×撮影対象物までの距離×2
例えば、下記の条件で撮影が可能となる範囲を計算してみましょう。
- 撮影したい対象物までの距離が6メートル
- 防犯カメラの水平画角が90度
この条件で計算すると、下記のようになります。
撮影可能範囲=1×6×2=12
つまり、水平画角が90度の防犯カメラで、撮影したい対象物までの距離が6メートルのケースでは、水平方向の撮影可能範囲は12メートルとなります。これは水平画角だけではなく、同様の計算をすることで垂直方向の撮影可能範囲も計算することができます。
防犯カメラを設置するポイント
防犯カメラの撮影可能範囲を求めることができたら、防犯カメラをどのように設置するといいのか、判断することもできます。そのほかのポイントも含めて、防犯カメラを設置する4つのポイントについて解説していきます。
防犯カメラの設置台数を計算する
防犯カメラの撮影可能範囲がわかると、必要なカメラの台数も把握することができます。1台で足りない場合は、何台必要なのか、などもわかるようになります。計算式は下記になります。
先ほどの一例を用いて、必要な台数も計算してみましょう。例えば、撮影したい水平方向の範囲が60メートルの場合、購入予定の防犯カメラの水平方向の撮影可能範囲が12メートルであれば、下記のような計算になります。
つまり、防犯カメラは最低でも5台を設置する必要があるということになります。ただし、防犯カメラを均等に設置できる条件が揃っている場合です。均等に設置できない場合や、棚や建物、障害物などによって死角ができる場合は、さらに台数が必要になります。
目的に応じた撮影可能範囲を把握する
防犯カメラはセキュリティ強化のために設置するケースがほとんどですが、それ以外の目的でも設置することがあります。そのため目的に応じた撮影可能範囲を考えて、機種を選ぶようにしましょう。
例えば、マンションの出入り口などに防犯カメラを設置する場合は、出入りする人物の顔などの確認ができるようにする必要があります。不審者の出入りを防いだり、確認するのが使用目的になるからです。この場合、撮影対象者に焦点が当たるように防犯カメラを設置する必要があります。つまり、それほど広い撮影範囲は必要ないということなのです。
一方、駐車場は敷地内に車が停めてあり、利用者の行き来も多くあります。そのため、可能な限り幅広い範囲を撮影できる機種がふさわしいと考えられます。このように目的に合わせて、どのような映像を残したいかも考えた上で機種を選び、設置するようにしましょう。
赤外線が届く範囲が撮影可能範囲となる
夜間などの暗闇を撮影する場合、赤外線を照射して撮影をする機種があります。このようなタイプの機種は、昼間と夜間の撮影可能範囲が異なるケースがあるため注意が必要です。防犯カメラ自体の撮影可能範囲が広くても、赤外線が照射されていない暗闇の箇所を撮影することはできないからです。
つまり、夜間にも防犯カメラを稼働させる場合は、撮影可能範囲を計算するのに加えて、赤外線が届く範囲も確認して購入・設置することが必要です。一般的な赤外線カメラは20メートル程度まで照射が可能ですが、機種によっては200メートルほど遠くまで照射することが可能です。
専門業者に相談しながら決める
これまで紹介してきたように、防犯カメラの撮影可能範囲を計算するには画角や焦点距離、レンズの種類、対象物までの距離といった専門的な知識が必要な上に、少し難しい計算をしなければなりません。また計算ができたとしても、それに相応しい防犯カメラを見つけて、正しく設置する必要もあります。
つまり、防犯を目的に防犯カメラを導入しても、本来の役割を果たせない可能性もあるのです。防犯カメラが正しく設置されていなければ、欲しい映像を残すことができないからです。
そのため防犯カメラに関する知識が豊富な専門業者に相談しながら購入したり、お任せする方が購入した後も安心と言えます。ぜひ信頼できる専門業者に相談するようにしましょう。
撮影可能範囲を正しく理解しないと防犯効果を下げてしまうことも
今回のコラムでは、防犯カメラの撮影可能範囲について解説しました。撮影可能範囲を把握するには、レンズの画角と撮影対象物までの距離を確認することが必要です。防犯カメラを購入する際はパッケージなどを確認し、必要な範囲を撮影できるか、正しく判断するようにしましょう。
特に広い場所を撮影したい場合は、適切に計算をして、必要な防犯カメラを選ぶことが大切です。撮影できない場所ができると防犯効果は極端に下がってしまいますので、不安な場合は専門業者のアドバイスを受けるようにしましょう。
- 2024.12.11
- 11:50
- 防犯カメラに関するお役立ちコラムはこちら